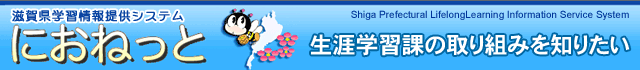![]() 平成18年度実施企業・団体 講演開催報告:
平成18年度実施企業・団体 講演開催報告:
実施企業・団体名 |
開催日時 |
|
|---|---|---|
| 株式会社 村田自動車工業所 | 平成18年7月10日(月) | 17:30~18:30 |
| 三恵工業 株式会社 | 平成18年7月19日(水) | 17:30~18:30 |
| 作新工業 株式会社 | 平成18年11月2日(木) | 17:00~18:30 |
| 積水樹脂 株式会社 滋賀工場 | 平成18年11月10日(金) |
13:30~14:30 |
| 株式会社 クリスタル光学 | 平成18年11月23日(木・祝) |
12:30~13:30 |
| 積水化成品工業 株式会社 滋賀工場 | 平成18年12月5日(火) | 14:00~15:30 |
| 滋賀トヨペット株式会社 | 平成19年1月12日(金) | 18:00~19:00 |
| ワボウ電子 株式会社 | 平成19年2月16日(金) | 17:00~18:00 |
| 株式会社 麗光 栗東工場 | 平成19年2月20日(火) |
15:00~16:00 |
| 同和問題企業連絡会 湖北ブロック | 平成19年2月23日(木) | 15:00~16:30 |
| 長浜キヤノン 株式会社 | 平成19年3月7日(水) |
17:20~18:50 |
| 高橋金属 株式会社 | 平成19年3月9日(金) | 12:30~13:30 |
| 日本ソフト開発 株式会社 | 平成19年3月10日(土) | 10:00~11:30 |
| パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社 | 平成19年3月19日(月) | 17:30~18:30 |
株式会社 村田自動車工業所
- 演題:「子どものほめかた・叱り方」
- 講師:滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 社会教育主事 山本広孝
- 開催日時:平成18年7月10日(月) 17:30~18:30
- 参加者:18名
- 講演内容:
○まず「子どものほめかた・叱り方」というテーマについて確認。続いて「となりをほめる他己紹介」(アイスブレーキング)をしながら、面と向かってほめることの照れくささと、言葉で伝えることの大切さを伝えあう。
○資料を活用した「語り合い」(グループ)を行う。ほめることで子どもがよい方向に変わったという経験や自分がほめてもらってうれしかった経験などを出しあう。ほめ方、叱り方のポイトを各自がメモし、グループ内でポイントだと思ったことを交流。
○結果よりも行動(過程)をほめること、ほめるときに他人と比較しないこと、本気で相手の事を思ってほめたり叱ったりすること、感情的に叱らないこと、また、叱った後きちんと理由を説明することなどを話しあう。(資料:よりよい子育てのためのヒント)
三恵工業 株式会社
- 講師:滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 社会教育主事 山本広孝
- 開催日時:平成18年7月19日(水) 17:30~18:30
- 参加者:16名
作新工業 株式会社
 演題:「子どもとともに親育ち~子どもの心の声を聴く~」
演題:「子どもとともに親育ち~子どもの心の声を聴く~」- 講師: NPO法人CASN代表 谷口久美子 氏
- 開催日時:成18年11月2日(木) 17:00~18:30
- 参加者:10名(男性6名 女性4名)
- 講演内容:
○子どもの人生の伴走者になりたいとの願いからCASNを設立し子ども専用電話「しがチャイルドライン」の開設など子どもの大人への成長を支援している。
○電話では、子どもが先生や親の悪口を言うケースはなく、むしろ、親や教師の期待に応えられない自分を責め、自己肯定できずに苦しんでいる。親はそのような、子どものことを全部わかっている気になっているが、親と子の間に大きなギャップがある。
○聞いてもらえた、寄り添ってもらえたという実感があれば、子どもはそこから自分の力で歩んでいける。お説教や励ましより、まず子どもの話に耳を傾け、思いを受けとめよう。
後半はペアになり、活動を通して聴き方について学んだ。
積水樹脂 株式会社 滋賀工場
 演題:「今、子育てで大切にしたいこと」
演題:「今、子育てで大切にしたいこと」- 講師: 野洲市教育研究所 副所長 南出 儀一郎 氏
- 開催日時:平成18年11月10日(金) 13:30~14:30
- 参加者:32名(男性24名 女性8名)
- 講演内容:
○青少年の悪い部分の報道に惑わされず、子どもをきちんと見よう。
○おばあちゃんや近所の人などに子育てを支えてもらうことも大切だ。
○期待に応え、いい子を演じようとすることが、ストレスをためることになる。子どもの内面を理解している必要がある。
○「早寝・早起き・朝ごはん」など基本的な生活習慣を身に付けさせることが体にも、学習にも大切だ。
○体験不足の子が多い。生活の中にある体験につながる素材と子どもを出会わせよう。
○人間は、ほめられて、次も頑張ろうと思える人の方がずっと多い。誉められることは明日へのエネルギーとなる。
○先生と子どもをうまく出会わせ、好きにさせていこう。
株式会社 クリスタル光学
 演題:「子どもとともに親育ち~子どもの心の声を聴く~」
演題:「子どもとともに親育ち~子どもの心の声を聴く~」- 講師: NPO法人CASN代表 谷口久美子 氏
- 開催日時:平成18年11月23日(木・祝) 12:30~13:30
- 参加者:26名(男性18名 女性8名)
- 講演内容:
○子どもの人生の伴走者になりたいとの願いからCASNを設立し子ども専用電話「しがチャイルドライン」の開設など子どもの大人への成長を支援している。
○電話では、子どもが先生や親の悪口を言うケースはなく、むしろ、親や教師の期待に応えられない自分を責め、自己肯定できずに苦しんでいる。親はそのような、子どものことを全部わかっている気になっているが、親と子の間に大きなギャップがある。
○子どもの育ちには、異年齢の集団の遊び、自分のことを見てくれる地域の大人、気が済むまで遊べる時間や空間、楽しさを心から共有できる仲間が必要だ。
○聞いてもらえた、寄り添ってもらえたという実感があれば、子どもはそこから自分の力で歩んでいける。お説教や励ましより、まず子どもの話に耳を傾け、思いを受けとめよう。
積水化成品工業 株式会社 滋賀工場
- 演題:「相談からみる「子どもの言い分」 」
- 講師:臨床心理士聖泉大助教授 高橋啓子 氏
- 開催日時:平成18年12月5日(火) 14:00~15:30
- 参加者:25名(男性22名 女性3名)
- 講演内容:
○子どもたちの家庭での様子を子どもの絵などから見ると、一人で食べていても、作った人の愛情を感じていたり、家族で食べていても、家族関係がよくないと心が落ち着いていないなどの例がある。
○親から一方的に子どもに指示や注意されるために、認めてもらえなかったり不満がたまっていたりすることが、多くの相談事例に見受けられる。
○母親まかせの中で、子育てに母親が悩んだり、母親の価値観だけでみられている子どもが息苦しさを感じたりしている。
○夫婦が互いにパートナーのことを理解し合い、父親も積極的に子育てにかかわることが大切だ。
滋賀トヨペット
 演題:「親の出番」
演題:「親の出番」- 講師: 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 美濃部俊裕
- 開催日時:平成19年1月12日(金) 18:00~19:00
- 参加者:35名(男性33名 女性2名)
- 講演内容:
○滋賀県のいじめのデータ現状から『いじめ』の話題を切り口に、いじめへの気づきが大切であることを確かめる。
○いじめの対象、標的が変わることもあるが、いじめられている子どもに応援する仲間づくりを行う。また、保護者も巻き込み協力体制の幅をつくる。
○親同士の話し合いで解決する場合もあり、いじめられている子どもを孤立させないということがポイントになる。
○不登校の生徒指導の話題から、子どもの心の荒れや病は、親の行き詰まりなどが子どもに対する影響力が非常に大きい。
○親子での挨拶や言葉がけが大切であり、5分でも10分でもコミュニケーションが必要である。
ワボウ電子 株式会社
 演題:「子どもの心と身体を健やかに育む」
演題:「子どもの心と身体を健やかに育む」- 講師: 東近江地域振興局 健康福祉部長 角野文彦 氏
- 開催日時:平成19年2月16日(金) 17:00~18:00
- 参加者:30名(男性9名 女性21名)
- 講演内容:
○心は「自分らしさ」が底面「知・情・意」が側面の三角錐に例えることができ、そのバランスが大切だ。「自分らしさ」は欲求と様々な規制の間に生じる葛藤の繰り返しで育っていく。
○子どもは、親との絶対的な信頼関係、小さい子との関わりから育つ自制心などをもとに人間関係を広げていく。
○人に迷惑をかけてはいけない、自分でしなさいを強調しすぎると、「助けて」と言えない子になる。HELPを発信し、失敗を助けてもらった経験が人を助ける精神を養う。
○「叱る」だけでは子どもは縮む。子どものよさをきちんと認め「ほめる」と伸びていく。
○家庭は子どもにとって唯一リラックスできる場である。子どもが安らげるよう、親はいい笑顔で子どもに接していこう。
○子どもの病気等には、救急外来だけでなく適切な対応をしよう。
株式会社 麗光 栗東工場
 演題:「みんなで子育て 心育て」
演題:「みんなで子育て 心育て」- 講師: 児童文学作家 今関信子 氏
- 開催日時:平成19年2月20日(火) 15:00~16:00
- 参加者:20名(男性9名 女性11名)
- 講演内容:
○ナホトカ号の重油流出事故にまつわるエピソードには、子育ての進め方のヒントがある。
・幼い時は、大人が身体を張ってその命を守らねばならない。
・親に守られているという安心感があると、子どもは新しい世界に向かっていける。
・成長に伴い、親以外の人に託すことも、子どもを大きく成長させることになる。○自分を大切にしてくれる人の声での読みきかせは、子どもにとってうれしく、価値のあることである。
○自分の好きな人と心が重なるのは素晴らしいことである。感動を共にし、子どものよさを認めたりほめれたりすれば、子どもは伸びていく。
同和問題企業連絡会 湖北ブロック
 演題:「子育ち、親育ち、わたし育ち~「じんけん」を切り口にして~」
演題:「子育ち、親育ち、わたし育ち~「じんけん」を切り口にして~」- 講師:(財)滋賀県人権センター 小林 尉 氏
- 開催日時:平成19年2月23日(木) 15:00~16:30
- 参加者:66名(男性61名 女性5名)
- 講演内容:
○人から言われてうれしかった言葉に共通するのは、周りから受け入れられていると感じる(受容感がある)言葉であることだ。
○受容感が高まるほど自己受容ができ、他者受容もできるようになる。受容感と自己受容を含めたものが自尊感情である。
○自尊感情が高いほど、また被差別経験やその疑似体験が多いほど、人権感覚が高まり、いじめや意地悪をする頻度が下がる。
○自尊感情を育むために、子どもの話を聞こう。そうすれば子どもは様々な思いを言葉にする(言語化)。この循環を繰り返すことが、子どもの自尊感情を育み、子育ち、親育ちにつながる。
長浜キヤノン 株式会社
 演題:「子どもの心と身体を健やかに育む」
演題:「子どもの心と身体を健やかに育む」- 講師:東近江地域振興局 健康福祉部長 角野文彦 氏
- 開催日時:平成19年3月7日(水) 17:20~18:50
- 参加者:27名(男性16名 女性11名)
- 講演内容:
○心は「自分らしさ」が底面「知・情・意」が側面の三角錐に例えることができ、そのバランスが大切だ。「自分らしさ」は欲求と様々な規制の間に生じる葛藤の繰り返しで育っていく。
○子どもは、親との絶対的な信頼関係、小さい子との関わりから育つ自制心などをもとに人間関係を広げていく。
○人に迷惑をかけてはいけない、自分でしなさいを強調しすぎると、「助けて」と言えない子になる。HELPを発信し、失敗を助けてもらった経験が人を助ける精神を養う。
○「叱る」だけでは子どもは縮む。子どものよさをきちんと認め「ほめる」と伸びていく。
○家庭は子どもにとって唯一リラックスできる場である。子どもが安らげるよう、親はいい笑顔で子どもに接していこう。
○子どもの病気等には、救急外来だけでなく適切な対応をしよう。
高橋金属 株式会社
- 演題: 「みんなで子育て 心育て」
- 講師: 児童文学作家 今関信子 氏
- 開催日時:平成19年3月9日(金) 12:30~13:30
- 参加者:19名(男性8名 女性11名)
- 講演内容:
○ある小学校で、校長先生が病気と闘っている自分の話を子どもらにすると、子どもが口々に先生を励ました。全身で子どもにぶつかる大人の思いは、ちゃんと伝わると感じた。
○国によって美意識は異なることを海外の生活で痛感した。日本人は空間や空気も含めて美を味わう特徴がある。子どもは大人が醸し出す空気の中で育つ。家庭や地域でも、大人がいい空気をつくって子どもを育てよう。
○自分を大切にしてくれる人の声での読みきかせは、子どもにとってうれしく、価値のあることである。
○自分の好きな人と心が重なるのは素晴らしいことである。感動を共にし、子どものよさを認めたりほめれたりすれば、子どもは伸びていく。
日本ソフト開発 株式会社
- 講師:滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 社会教育主事 山本広孝
- 開催日時:平成19年3月10日(土) 10:00~11:30
- 参加者:6名
パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社
- 演題:「子どもとともに親育ち ~子どもの心の声を聴く~ 」
- 講師: NPO法人CASN代表 谷口久美子 氏
- 開催日時:平成19年3月7日(水) 17:30~18:30
- 参加者:31名(男性25名 女性6名)
- 講演内容:
○子どもの人生の伴走者なりたいとの願いからCASNを設立し、子ども専用電話の開設等により子どもの成長を支援している。
○電話では、先生や親の悪口を言うケースはなく、むしろ、親や教師の期待に応えられない自分を責め、自己肯定できずに苦しんでいる。親はそのような、子どものことを全部わかっている気になっているが、親と子の間に大きなギャップがある。
○子どもの育ちには、異年齢の集団の遊び、自分のことを見てくれる地域の大人、気が済むまで遊べる時間や空間、楽しさを心から共有できる仲間が必要だ。
○人は自分のことに理解を示してくれると安心感が生まれ、変わることができる。人は甘えと反抗を繰り返しながら自立していくものである。
○親と子だけの関係でなく、そこに友達や地域の人など第三者が入っていることが、子どもが育つ上で大事だ。