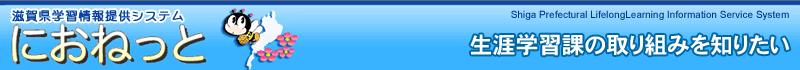長浜市立びわ南小学校から「親子活動として近くの川で水環境の学習をするので、『学校支援メニュー』の中の講師の方に来ていただきたいです。」とご相談がありました。そこで、水環境を考える学習の支援等を行っておられる講師の方をご紹介しました。 今回の活動は次のような目的で計画されました。
講師の方は、自然環境においてさまざまな活動を行っておられます。今回は地域の河川にすむ生物の観察会を行うことの目的や内容、水生生物を捕る際のポイントなどを教えてくださいました。 水生生物を捕る際のポイント 環境が違う4地点で、水生生物を捕って調査 学校に戻って、捕った水生生物の観察会
まず、アユとアメリカザリガニが大量に捕れたことにびっくりしました。ただ、アメリカザリガニやブルーギル、オオカナダモなどは、外来種といって外国から人の手によって持ち込まれた生物です。外来種は、元々日本にいた生物や生態系に悪影響を及ぼしていますので、特に外来魚はリリース(再放流)禁止がルールです。 今回、調査した川は姉川の近くで、特に上流はきれいな水が流れているそうです。あまり魚捕りはしないという子も多かったのですが、子どもたちは身近にこんなに色々な生物がいることに、とてもびっくりしていました。 |
|
|
|
|
|
|
掲載日:2010年8月6日

| 「親子川の生物観察会」 | |
| 長浜市立びわ南小学校4年生 | |
| 滋賀の理科教材研究委員会 | |
| 平成22年7月10日 | |
| 親子活動(総合) |