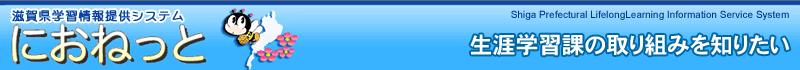野洲小学校で、バリアフリー教室が行われました。今回受講する4年生は、地元の総合デイサービスでお年寄りの方のお手伝いをしたり、校舎内での高齢者体験をしたり、これまでにも積極的に福祉の学習に取り組んできたので、今回は、その学習を深める事がねらいとされました。 体験学習の場は、運動場と最寄りの野洲駅です。体験学習は、そこへ行くまでの往復の路上で2班に分かれます。体験はクラスごとで交代をして行いました。 まず、体育館でオリエンテーションが行われ、講師の方が「今日は、困っている人を見かけた時に、お手伝いしましょうか?と話しかけるきっかけを作ってほしいと思っています。」とお話されました。 あと1つの班の児童は、学校から車いすで近くの野洲駅へ行きます。一般道路なので、通行人に迷惑がかからないよう、また、危険行動がないよう注意を受けて、出発しました。 最後に体育館で、「みなさんしっかり話を聞いて、真剣に取り組んでくれました。今日の体験を心に残して、これからは、町で体の不自由な人をみかけたら、まず“こんにちは”と声をかけてあげてください。“こんにちは”の一言が、体の不自由な人はとてもうれしいと思っています。」と講師の方が感想を述べられ、代表児童に修了証が授与されました。 |
|
|
|
|
|
|
掲載日:2011年1月7日

| 「バリアフリー教室」 | |
| 野洲市立野洲小学校4年生 | |
| 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局 後援:社団法人滋賀県バス協会、協力:滋賀県教育委員会、滋賀バス株式会社、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会、西日本旅客鉄道株式会社、野洲市、野洲市教育委員会 |
|
| 平成22年12月3日 | |
| 総合的な学習の時間 |