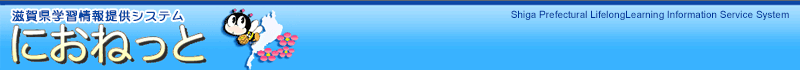|
1.公民館利用の現状と問題点について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.公民館の配慮と施設利用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58年度における市町村立公民館の数は、中央館45館、地区館100館、分館は41館あり、類似施設が3館ある。 公民館を設置する市町村の数は類似施設を含むと全市町村にあり、ちなみに小学校区における中央館・地区館の設置率は66.5%になっている。 公民館の設置は、「『公民館の設置及び運営に関する基準』の取扱いについて」においては、利用上の効率が最も高い対象区域は「16km2以内」とされているが、地域の実情によって決められるもので、県内50市町村の配置は次のとおりである。
◎夜間利用 民間の開館の後、続いて夜間の公民館利用は多く、それに対応する公民館職員の配置にもいろいろ問題をかかえている。 公民館において夜間利用がある場合、職員の時差出勤・代休振替措置・時間外勤務等の方法がある場合、職員の時差出勤・代休振替措置・時間外勤務等の方法が講じられたり、住込みの用務員任せや使用団体の責任者に依頼するなどさまざまで、一部警備保障制度がとられているところもある。
◎開館・閉館時刻
◎休館日 公民館の多くは、日曜日または月曜日を休館日としている。
◎貸館 公民館の貸館利用については、「休館日は貸館なし」と決めている公民館も、市町村で開催される事業等の関係から特別に配慮して貸館している場合も見られ、多くは職員が出勤している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.学習活動に関する問題点
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.参加者の固定化について
学級・講座・教室の学習活動への参加者がややもすると限られた人たちを中心としたものになりやすい。 2.今日的課題への志向促進について 学習内容に趣味や生活技術といった実技的なものの学習に比べて、身近な生活課題や地域課題の取上げ方に弱さが見られる。 3.学級・講座の企画・立案等について 住民参加による主体的な学習が呼ばれながら、学級・講座の企画・立案・運営等がややもすると公民館にまかされがちになる。 4.学習体制について “魅力ある学習は公民館活動の活性化につながる”といわれながら、学習形態や方法・内容等の工夫に弱さが見られる。 5.高齢者への学習機会について 人口の高齢化に対処した学習機会の提供について、学習内容の対応化が遅れがちになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.管理運営に関する問題点
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.公民館の機能・役割について
現代社会が要求する公民館の機能や役割についての理解や認識に不十分さが見られる。 2.貸館利用について 地域住民の学習の拠点である公民館がややもすると主催事業と離れて貸館を中心に運営されているところが見られる。 3.専任職人の現状について 公民館において常勤で専任の職員が確保されていない所がある。 4.公民館職員の勤務体制について 土 ・日 ・夜間の出勤に対して十分な配慮がなされていないきらいがある。 5.各種関係機関・施設との連携について 一公民館の持っている機能に頼っているだけでなく、広く交流を考えたり、補い合うなどの連携が弱い。 6.日曜・祝日の公民館利用について 日曜や祝日が休館になっている公民館では、身近にある公民館であるのに利用できない地域住民は数多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目次へ |