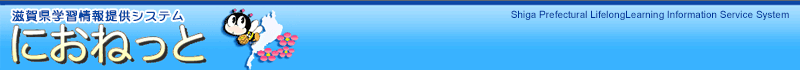1 子供をとりまく現状と課題 |
ふつう、家庭教育とは「親が未成年の子に対して行う教育である」と解されている。しかし、家庭教育は親が行うだけでなく、家庭内の雰囲気や家族との人間関係、家族各人の生き方や生活なども子どもの考え方や行動に大きな影響を与えている事は事実であり、家庭教育をひとり親のみが行う教育であると解するのは早計であろう。ただ、親として「子どもに対していかなる家庭の雰囲気を作るか」「外部に対してどのような関係をもつか」といった家庭を中心とした広い視野と識見を持つことが必要であり、この事が教育として欠かせない温かい配慮であると思われる。 物の豊かさに左右された生活や父親の家庭内での姿の希薄化、母親の家庭外就労の増加(昭和59年度版労働白書)家庭の主婦の日常生活、ライフサイクル変化、人間的なふれ合いの希薄化、地域連帯意識の欠如等変容のめまぐるしい現在の社会で家庭、地域社会の事態の変化に親の家庭教育への対応がおくれているのが現状であろう。 また、少子化や子どもを家庭の労働力として扱う必要がなくなってくるなどの社会変化と相まって、家庭内での教育機会が少なくなり、勤労体験や家庭の一員としての自覚、自制心が育ちにくくなってきている。 こうした観点から家庭教育の重要性にかんがみ、県では公民館における家庭教育学級やPTAの指導者研修事業の充実をはじめとして家庭教育啓発資料の配付、テレビによる親子映画劇場の鑑賞を通して親子の対話促進をはかるなど各種の事業に取り組んでいる。また、本年度からは3歳児をもつ親を対象にはがき通信、テレビ放送、巡回面接接相談等あゆっ子通信による家庭教育事業を実施しており、意外に大きな反響が認められる中で更により広くより多くの人々に浸透をはかる手だてを講ずることが今日的な課題である。 |
| 目次へ |