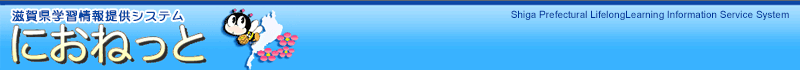1.活性あるまちづくりをめざす公民館 |
| 市町が設置する地域における生涯学習・社会教育の中核的な施設である公民館は、類似施設を含め本県には211館あり、地域の実情も加味しながら、実に多種多様な事業が実施されており、地域コミュニティを形成し活力ある地域づくりを進める上で、公民館が果たすべき役割は大なるものがある。 そこで、地域の特性を生かしつつ、住民主体の活力あるまちづくりを進めるために公民館のあるべき姿を整理した。 (1)社会的課題に関する学習機会の充実とネットワークの形成 公民館調査の結果によると、公民館が主催する講座は、趣味的・教養的な課題を主とした学習内容が約半数を占めている。加えて、長年同一の講座を同一の形態で実施されていることから、参加者が限定されている傾向が見受けられる。 今後は、例えば、「団塊の世代」が一斉に退職期を迎えることから労働人口や地域社会に変化が生じる2007年問題など、社会的課題をテーマとした講座内容の学習機会も設定していくことが求められる。 また、講座などの企画・実施にあたっては、参加体験型研修の導入、グループ別討議や交流の場づくりなどにより住民が参加したくなり、学習の成果が次の新しい課題学習へと高まるようなしかけづくりも重要である。なお、講座提供については、受益者負担の原則について検討することも大切である。 さらに、関係各機関や社会教育関係団体・NPO・総合型地域スポーツクラブなどさまざまな主体とのネットワークの形成を図り、連携・協働した新たな取組みや各主体の特色・個性を生かした事業も必要である。 それらの取組みによって、地域の実情に応じた課題の設定や事業内容の充実、参加者の広がりなどに繋がることが期待される。 |
連携・協働による事業のネットワーク化甲賀市の信楽公民館では、各公民館、学校、NPO、陶芸の森、ミホミュージアム、自治会、スポーツクラブ、子ども会など多様な人々や団体と連携し、それぞれの特性を活かした国際教育に関わる事業などを積極的に展開されています。地域の社会的課題に対する取組みや世代間交流を活発にし、元気なまちづくりを目指した連携・協働による事業のネットワーク化は公民館に求められる課題となっています。 |
 「外国人講師による食文化講座」(信楽公民館) |
(2)学習情報の収集と提供の工夫 公民館は人が集まるところ、人がいてはじめて息づくところであり、したがって、人が気持ち良く長く過ごせるための物的・人的な工夫をすることは、公民館の重要な仕事である。住民が気軽に立ち寄れ、居心地の良い公民館とするために、例えば、気軽に情報収集ができたり、利用者同士の交流が図れるようなコーナーを設置し、住民にとって居場所となるような工夫も求められる。 現在、公民館からの情報は、公民館報や市町の広報誌、募集チラシなどにより発信されているが、多様化・高度化する住民の学習要求に対して、的確に対応していくため、提供内容や手段について一層の充実を図ることが必要である。 このため、住民がどのような学習情報(学習内容・学習機会・学習資料・人材・学習活動プログラム・団体やサークル・学習拠点・先進的な取組み事例・関係機関の情報など)を求めているかの把握を行った上で、公民館サポーターなどのボランティアに協力を求めて、必要な情報の収集、適切な情報の提供、学習情報誌の発行、ホームページの開設などといった工夫も考えられる。 また、インターネットを活用することで関連するさまざまな情報収集も可能であり、住民が気軽に利用できるようインターネット環境の整備を図ることが必要である。県域の学習情報については、滋賀県学習情報提供システム「におねっと」(http://www.nionet.jp/)の活用が有効である。 このようなさまざまな情報提供手段の充実を図ることにより、情報を得るための相談が増加し、ひいては住民の主体的な活動が促進されるものと考えられる。 さらに、公民館は、住民が気軽に学習相談ができる雰囲気づくりに努めるとともに、人と人をつなぎ、また、さまざまな団体と団体をつなぎ、住民の学習成果が活用されるような支援をしていくことも求められている。 また、新聞などのマスメディアに公民館での取組みや住民の活動が取り上げられることは、学習や活動の活性化に有効な手段であり積極的に活用すべきである。 |
住民の交流の場となるラウンジ米原市の近江公民館には、子どもから高齢者までの交流の場となる、ラウンジが設けられています。開放的な吹き抜けからのひかりあふれる空間は、楽しい会話が弾み、新しい出会いの場ともなっています。住民にとって快適な「居場所」と言えるラウンジには、自主サークル制作による作品など身近な情報コーナーも設置され、幅広い年齢層の住民が、活動を展開する拠点としての賑わいがあります。 また、近江公民館では「いつでも、だれでも、気軽に」をモットーに公民館が運営され、毎週第1土曜日を「わいわいサタデー」と銘打って、公民館や隣接するグラウンド・体育館を無料開放されています。 |
 「子どもたちで賑わうラウンジ」(近江公民館) |
(3)事業の計画・目標・評価 平成15年の「公民館の設置及び運営に関する基準」の全面改正により、「公民館は事業の水準の向上を図り、当該公民館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、公民館運営審議会などの協力を得つつ、自ら点検および評価を行い、その結果を地域住民に対して公表するよう努めるものとする。」と定められた。 したがって公民館には、その役割を達成するため、到達目標を明確にした上で事業を計画し、常に検証する姿勢を大切にしつつ実践化を図っていくことが求められている。 そこで、例えば、参加者の満足度のみに終始するだけではなく、参加していない人やグループ・組織に属していない人への手だてができているか、また事業の展開が地域づくりにどのように結びついていくのかといった視点で総括をすることも大切である。 (4)職員の資質向上 公民館は、地域づくりとそれを支える人と人の関係づくり、また活動を実践する人材の育成や支援を行う場であり、そこには一定の施策や設備が必要であるが、何にも増して重要なのは、そこで働く職員である。活動が活発な公民館には、自分の仕事に自信と誇りをもって成し遂げ、利用者からも頼られる職員がいる。 公民館職員に求められる能力は、社会教育全般の専門的な知識のほか、事業の企画力、組織力、実行力、情報収集能力、調査分析力、コミュニケーション能力、コーディネート能力など多岐にわたる。このため、公民館職員としての資質を高めるには、日ごろから自己研鑽に努めるとともに、何よりも住民の生の声に接することができるよう地域の現場に足を運び、地域の実態を知り、人に出会い、情報を得ることが重要である。 また、県教育委員会や県公民館連絡協議会等が主催する研修会などへ積極的に参加し、知識やスキルを高めたり、交流を通して職員間のネットワークを築くことも重要であり、館長のリーダーシップにより参加しやすい職場づくりが必要である。 さらに、市町の教育委員会事務局には必置とされている社会教育主事についても資格取得のための講習会が毎年開催されており、公民館職員においても積極的な取得が望まれる。 |
職員の資質向上を目指した研修会の開催大津市教育委員会では、毎年市内の32の公民館職員を対象に「社会教育担当職員研修会」が開催されています。 滋賀大学生涯学習教育研究センターと連携し、公民館活動の指導、助言をいただいたり、市内外の先進的な取組みを展開されている公民館から実践事例の発表がなされ活発な討議が行われるなど、充実した研修がなされています。公民館に携わる職員としての資質を高める場となり公民館同士の連携を深める上でも貴重な研修と言えます。 |
 「社会教育担当者研修会」(逢坂公民館) |
(5)社会教育委員等との関わり 平成11年の社会教育法の改正により公民館運営審議会は、各自治体の特色が生かせるよう、必置が緩和され任意設置となり、地域の実情に応じた住民の意思を反映させる新たな組織や仕組みづくりが可能になったが、公民館調査によると公民館運営審議会等の外部委員による公民館運営に関わる組織が設置されているのは約半数にとどまっている。 そこで、地域における社会教育の実践者である社会教育委員をはじめ、自治会関係者、民生児童委員、体育指導委員など幅広い活動の担い手と連携した、民意をより良く反映した組織づくりや仕組みづくりが望まれるところである。 (6)指定管理者制度と公民館の運営 地方自治法が改正され、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減などを図ることを目的として、平成15年9月より「指定管理者制度」が導入された。 公民館についても本制度の対象となり、従前から外郭団体への管理運営委託を行っていた公民館については、経過措置期限の平成18年8月までに制度導入が必要となっている。 今後は、直営の公民館においても制度導入の可否が検討されることになるが、まずは自治体自身が、公民館運営に対する明確なビジョンと方向性を持っていることが重要であり、その検討にあたっては、施設の貸し出しや講座の実施のほか、住民活動への支援により人づくりをとおしたまちづくりの振興の維持など、さまざまな公民館としての役割が確保され、適正な運営が展開できるかどうかという視点での議論が重要である。 また、公民館からコミュニティセンターへ移行する場合にあっても、社会教育活動の充実が維持され、住民サービスの向上が図られた運営が確保されることが望まれる。 |
| 目次へ |