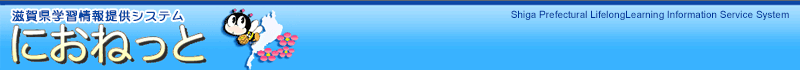2.公民館に求められる「今日的な課題」
|
生涯学習は非常に幅広い分野が対象となるが、公民館には、地域や社会に役立つ取組みが求められており、地域住民とともに取り組む今日的な課題について整理した。 (1)家庭や地域の教育力の向上 少子高齢社会と核家族化の進展、また地域コミュニティの希薄化などから子育ての孤立化が進む中で、子育てに自信がないという親が増加しており、家庭や地域の教育力を育む必要性が問われている。 家庭教育の学習機会の提供に関して、公民館調査では、すでに約6割の公民館において実施されているが、子育てや家庭教育に対する支援、学校週5日制実施を契機とした地域の教育力を高めるための子どもの居場所づくりおよび学社連携・融合による体験活動などは、今後も公民館が拠点となり、一層充実したものとしていく必要がある。 次代の担い手となる子どもたちを健やかに育てることは、親や家庭はもとより、社会全体の責務といえる。住民一人ひとりが、また企業やさまざまな団体が、家庭における子育てを支える一員としての自覚を高め、子どもを「社会の宝」として、家庭、学校、地域、企業などが連携して、社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりを進めていく必要がある。公民館はその気運醸成の拠点またコーディネート役として、その役割を果たしていくことが期待されている。 |
「地域協働合校」の理念を生かした
|
 「いきいきクラブ」(笠縫小学校) |
(2)青少年の体験活動の推進 青少年が多種多様な課題を克服するには 、その成長過程においてさまざまな人々との関わりや体験をする機会を得ることが重要である。それら機会を通して、自らの言動が社会に認められることで、社会の一員としての自覚が生まれ、よりよく生きるための自信を持つことに繋がるものと考える。 そのために、青少年が地域のさまざまな世代の人たちとともに 、主体的に地域の諸課題を考え、解決していくための活動に取り組んでいくことが重要であり、それが青少年の規範意識や自尊感情を育み、社会的自立を促進していくことにつながる。 青少年を対象とした学習機会については、すでに約7割の公民館において実施されているが、残る約3割の公民館においては事業がなされておらず、公民館により取組みに差が生じていることは否めない。 このため、事業への青少年の参加率や参加頻度、充足感や達成度などについて総括を行い、参加者の顔ぶれが固定化しないためのしかけづくりやより主体的な参加が図れるような体験学習の導入などにより、青少年の「生きる力」が育まれるような取組みを進めていくことが求められる。 また、青少年の体験学習で身につけた力が、まちづくりのために生かされ、自己実現が図れるよう、大人と子どもの架け橋としての活動ができる機会やしかけづくりにも取り組む必要がある。 |
青少年の生きる力を育む「通学合宿」の拠点高島市の高島公民館アイリッシュパークでは6泊7日の通学合宿が実施され、合宿生活をとおして働くことや協力することの大切さを子どもたちは体験しながら学びます。青少年の自立を支援する取組みとして「合宿サポーター」をはじめとした、世代を超えた数多くの地域ボランティアの方々の支援を受けながら事業が展開されています。 「通学合宿」 地域の公民館などで、一定期間寝泊まりしながら学校に通う取組みです。食事や洗濯など自分たちの身の回りの日常生活に関わることは、子ども自らが行います。 この活動を地域の青年や大人が支えることは、子どもを中心にすえた地域づくりのよいきっかけにもなります。 |
 「食事の準備」(高島公民館) |
(3)安全・安心のまちづくり 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例が平成15年4月にスタートした。 県民一人ひとりが自らの安全は自らが守るという意識を身につけるとともに、身近な地域社会において相互に連携・協働を図りながら、だれもが安心して生き生きと暮らせる安全な社会の実現に向けて主体的な取組みを進めていくことが重要である。 犯罪を防止する支援システムの体制として、市町や学区などを単位とした推進体制の整備が促進されており、地域づくりの活動拠点としての公民館の役割は、大きなものがあるといえる。 また、防犯・防災はともに発生時にいかに迅速かつ正確に対応できるしくみが整っているかが問われており、日常からの連携した取組みや継続的なマニュアルの点検作業等の体制づくりが大切である。 そこで、地域の実情に応じた対応策の検討とともに「地域安全マニュアル」や「通学路安全マップ」の作成にかかるコーディネート、さらには安全パトロールの拠点としての機能、スクールガード(学校安全ボランティア)など防犯ボランティアの組織化に向けた働きかけなどに、住民とともに関わり取り組むことが望まれる。 |
安全・安心のまちづくりと公民館の関わり草津市では、安全・安心して暮らせる地域づくりをめざして「地域安全に関する条例」を制定し、草津市地域安全連絡協議会が立ち上がっています。公民館がその協議会の事務局となり、自治会や青少年育成会議、PTA等、構成団体の連絡調整を担っています。 |
 「下校指導」(笠縫東小学校門前) |
(4)主体的な取組みが期待されているその他の課題 公民館主催の事業や関係機関との連携・協働による事業の実施においては、これまでも重点的に取り組んできた人権、男女共同参画、郷土の歴史・文化など事業の充実とともに、対処が求められている食育や健康づくりの推進、環境学習、国際化への対応、介護予防への対応、司法制度・裁判員制度やニート支援、キャリア教育の推進などの新たな課題も、関係する機関と連携・協働を図りながら意図的・意識的に学習プログラムに組み入れることにより、地域づくりのために「役に立つ公民館」として適時的確な事業を住民に提供していくことが重要である。 |
「今日的課題」に対する連携した取組みの展開公民館主催の事業や関係機関との連携・協働による事業の実施においては、これまでも重点的に取り組んできた人権、男女共同参画、郷土の歴史・文化など事業の充実とともに、対処が求められている食育や健康づくりの推進、環境学習、国際化への対応、介護予防への対応、司法制度・裁判員制度やニート支援、キャリア教育の推進などの新たな課題も、関係する機関と連携・協働を図りながら意図的・意識的に学習プログラムに組み入れることにより、地域づくりのために「役に立つ公民館」として適時的確な事業を住民に提供していくことが重要である。 |
 「寿大学講座」(安土公民館) |
| 目次へ |