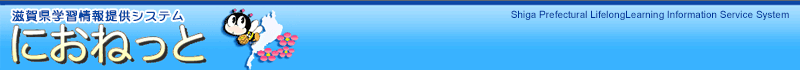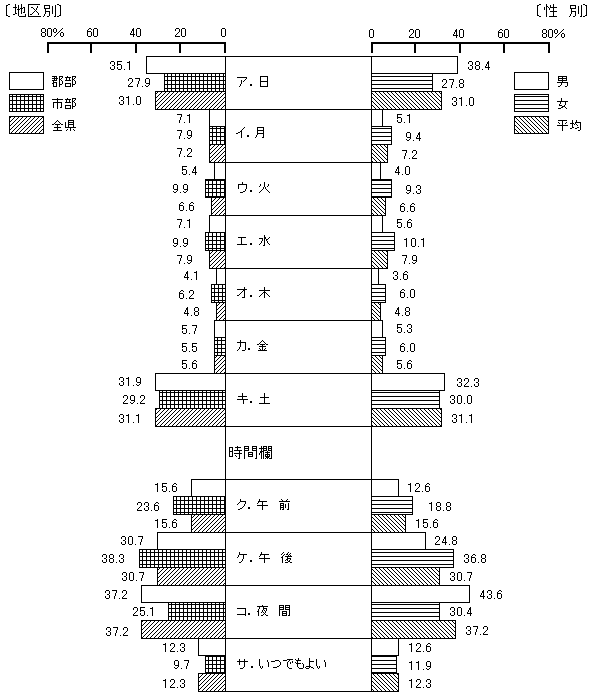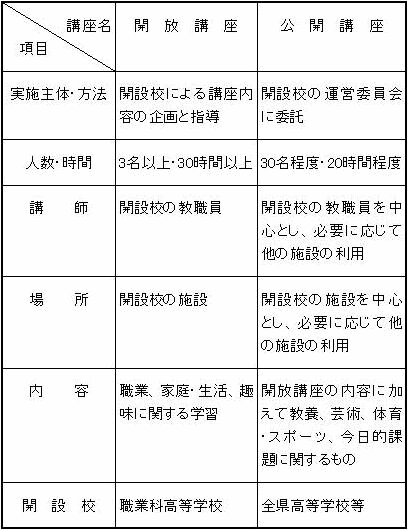2.(新規)高等学校等公開講座の具体的方策 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 高等学校等公開講座の基本的考え |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
今日、社会教育は人々の多様な学習要求に対応していくために各種の学習や体育・スポーツ活動、芸術文化活動など幅広く多様な学習機会を提供するよう求められており、生涯学習の観点からもその果たす役割は極めて大きいものがある。 本県では昭和57年より県内短期大学や公立高等学校の協力を得て、大学・高等学校開放講座や成人大学講座を開設し、一定の成果をあげている。 しかし、国の補助事業としての制約と現在、職業科高校においてのみ開設されている現状では、県民の学習要求の多様化、高度化に対応しきれていないという問題が指摘されている。そこで、次の二つの視点から公開講座の方策を検討した。 ア.生活水準を広め、深める場として 従来の開放講座の内容は職業生活、家庭・日常生活、趣味のそれぞれについての知識・技能の習得に関する学習が中心に展開されてきた。しかし、今後、これらの改善・充実に併せて、教養・芸術・芸能や体育・スポーツ、今日的課題等に関する学習機会の提供が強く期待されている。 このような県民の期待に応えるために学校開放を従来の職業科高校とさらに普通科高校にまで拡大して、地域社会に開かれたものにする必要がある。 そこで従来の開放講座で展開されてきた内容に加えて、語学や一般教養に関するもの、青少年問題、同和問題等の今日的課題に対処するもの、地域性・郷土色のあるものなどユニークな発想を盛り込んだ生涯学習の機会として県費単独事業「高等学校等公開講座」(以下「公開講座」と呼ぶ)の新設が望まれる。 イ.地域に根ざした学校として このように相互の信頼関係が受講者を通じて地域に波及していくことにともなって、地域住民の学校理解が深まり、地域の教育力の向上につながっているものと考えられる。 また、公開講座を開設する学校も、地域住民の生活課題を認識し、地域社会の経済、文化、自然、歴史等の教材化を図ることにより、生徒の地域への関心も高まるものと思われる。 一方、地域との交流は学校行事や生徒会活動、ボランティア活動等で積極的にすすめられているが、公開講座は生涯学習の場における学校、教職員、住民三者相互の交流といった側面も期待される。したがって、高等学校にとっても一方的な地域社会への奉仕でなく、地域住民と接することによって、高等学校の本来的な活動に大きな刺激を与えていくものといえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 高等学校等開放講座の企画と運営について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ア.講座の形態や運営等に関すること (受講対象者) (開設基準) (開設時期等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2)県民の生涯学習に関する意識と活動の実態調査(昭和57年 滋賀県教育委員会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたが、学習や活動に最も参加しやすい曜日を上欄に、時刻を下欄に、1つずつ選んでください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(運営委員会) (開設手順)
(受講費用) (募集・広報) 特に公開講座の趣旨、学習内容等は多くの県民が理解して意欲的に参加できるよう周知・徹底に努める必要がある。 広報活動の例として次のものが考えられる。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ.講師、講座分野等に関すること。 しかし、学習内容や学習方法によって公開講座の趣旨が損なわれない範囲で外部から講師を招いたり、開設校以外の場所で行うことも可能である。 外部講師を招へいする場合は高等学校教育研究会や他の高等学校等からの派遣、あるいは地域における有識者の協力などが考えられる。 なお、高等学校教職員を対象とした講師の名簿を作成していくことが望ましい。 (指導方法)
(講座分野) 表3 講座分野とその内容
(講座編成) 各編成を例示すると次のようになる。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 開放講座との相違点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
従来の開放講座と(新規)公開講座の相違点は次の表4のとおりである。 表4 従来の開放講座と(新規)公開講座の相違点
|
| 目次へ |